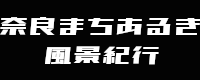滋賀県の県庁所在地である大津市と京都市を結ぶ鉄道路線としては、JR線に加え「京阪京津線」と呼ばれる路線が通っています。
京阪京津線については、大津市内~京都市内の日常的な移動に欠かせない存在である一方、びわ湖浜大津駅周辺で「路上」を通る区間があることから、その独特の風景が注目を集めることがあります。また、それ以外にも急勾配・急カーブ・地下鉄区間など目まぐるしく変化する特徴を複数持ち合わせた路線であり、鉄道路線としては日本でも特にユニークな存在と言えます。
こちらでは、そのような京阪京津線が有する特徴について、基本的な知識を解説していきます。
【路面電車】巨大な電車が路上を走る日本唯一の光景

京阪京津線の最大の特徴と言える点としては、大津市内に入ってからの一部の区間では完全な形で「道路上」を走行する「路面電車」となっている点が挙げられます。法律上も京津線は「鉄道」ではなく「軌道」に位置づけられており、同じ京阪電鉄でも本線・宇治線などとは位置づけは大きく異なります。
また、京津線の場合は単に路面を走るだけではなく、日本で最も「大型」の車両が「路面」を走るという特徴を持ち合わせています。通常路面電車と呼ばれる存在は、「車両の長さ」が「30m」を越えないという法律上の要件が定められていますが、京津線の電車は特例によって認められた「60m以上」の長さを持つ「4両編成」の大型車両であり、このようなケースは全国でもここだけとなっています。

路面区間は、JR大津駅寄りの位置にある「上栄町駅」を出てすぐの場所から、「びわ湖浜大津駅」までの区間、約700mの距離となっています。なお、京津線と連絡する「石山坂本線」については、「びわ湖浜大津駅前」の交差点付近を除き路面区間はありませんが、車両の大きさはむしろこちらの路線の方が小さいことが特徴です。

路面を走るため一般的な鉄道と異なり「信号」も道路に合わせた形になっており、上栄町~びわ湖浜大津駅間では途中で信号待ちをするために停車することも一般的です。
【登山電車】急勾配・急カーブを越えて京都方面へ

路面を走る区間を持つ京津線は、大津市内の路面区間を通り過ぎると京都市との境にあたる逢坂峠周辺を通ります。
この区間は、さながら「登山電車」のような特徴を持つ環境となっており、急勾配・急カーブが連続して見られ、大型の電車が通る路線としては全国的に見てもかなり異色の存在と言えます。
最も急な勾配は上栄町駅~大谷駅間で「61‰(パーミル)」の勾配区間(1,000m進めば61m上がるような勾配)があり、「鉄の車輪」で走り、ケーブルカーのように引っ張られる車両ではない一般的な鉄道としては、極端にきつい勾配(通常は35‰が限度)であり、車両はこの勾配に対応できるような高い性能を持つ設計となっています(製造コストは面積あたりでは一般的な鉄道車両よりもかなり高額)。

また、カーブについても「半径50m」を下回るような極端な急カーブが複数存在し、特に上栄町駅~大谷駅間にある「逢坂山トンネル」の東側入り口付近では、わずかな距離で向きを90度変えるようなカーブが見られ、電車は非常にゆっくりとした速度で進みます。
【地下鉄】路面を走った電車が京都市営地下鉄へ直通運転

京津線は、京都市内(山科区)に入りしばらくすると一部で急な勾配はあるものの、急カーブがない比較的直線的なルートを通ります。一方で、山科区の中心駅にあたる京阪山科駅を過ぎると、列車は「地下」へと入り地上を走らない「地下鉄」のような区間となります。
京津線は、かつては地上のみを通り現在の京阪三条駅付近まで結ぶ路線でしたが、京都市営地下鉄東西線の開業に伴い「御陵駅」を起点に地下鉄線と直通運転をする路線に変化し、山科駅を過ぎると地下に入るようになりました。
なお、大津方面~御陵駅までは「京阪線」の運賃となりますが、御陵より先の区間は京都市営地下鉄の運賃に切り替わります(一定の割引制度あり)。
まとめ
京津線を含む大津線の「便利な使い方」・「お得なきっぷ」については、上記の記事で解説しています。