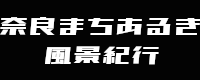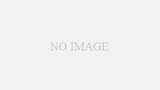春になれば雪国では必ず訪れる「雪解け」の季節。
雪は当然ながら雨水が凍ったものですので、解けて流れ始めれば地面や河川にとっては雨が降ったような場合と大きく変わらない状況が生じます。
こちらでは、雪解けが急速に進むことによって生じることがある「融雪洪水」について、そのメカニズムや北海道・札幌・日本国内で生じる可能性などを考えていきたいと思います。
融雪洪水のメカニズム・基本
| 発生の流れ | 1 急速な気温上昇や、気温が高い状態でのまとまった雨などに見舞われる 2 上記の原因で大量に積もった雪が一気に解けたり、雪の中に蓄えられていた水分が流れ出す 3-1 その結果として河川が増水し氾濫などを引き起こす 3-2 または水はけの悪い場所に水が溜まり浸水・冠水を引き起こす 3-3 河川が凍っていた場所の場合氷が川をせきとめる「アイスジャム洪水」を引き起こす ※日本国内で発生するものは主に3-2・3-3のパターン |
| 発生する場所 | ・積雪が多い地域で水はけの悪い場所 ・積雪が多い地域で川沿いの地域 ・積雪が多い地域の「下流域」 ・冬場に河川が「凍結」する地域 など |
| 発生する時期 | 通常春先(2月後半~4月頃) 日本国内の事例では3月に発生する場合が多い |
| 気象警報・注意報 | 洪水警報 融雪注意報 |
融雪洪水と一般的に言われるものは、積雪の多い地域で春先に発生することが通常です。
発生する場所は、積雪が多い地域の水はけの悪い場所・川沿いなどが基本ですが、河川が氾濫する場合は雪が少なくても「上流」で雪が多い場合発生の可能性がないとは言えません(但し、後述するように日本国内でその可能性は極めて低いと言えます)。
また、こちらも後述するように、川自体が凍結する場所は「アイスジャム洪水」として、割れて流れ出した氷が川をせきとめて発生する「融雪洪水」ならぬ「解氷洪水」とも言える現象が発生することがあり、こちらは北海道の中小河川などでは発生のリスクがあります。
融雪に関する災害が発生する可能性がある場合、気象庁は公式的な「全般(地方)気象情報」などの発表を行い融雪に伴う災害への警戒を呼び掛けるほか、一般的にも分かりやすいものとしては「洪水警報」や「融雪注意報」の発令を行い警戒を呼び掛けます。
積雪というものは、大雑把に言えば場所によって100~500mmくらいの量の「雨」が「氷」になって保存されているようなものです。それが一気に解け始めると、毎日数十mm単位の雨が降り続けるような状況と変わりありません。結果として河川は増水し、水はけの悪い場所では浸水・冠水などの被害が発生するリスクが生じることになります。
融雪洪水は発生するのか?【北海道の事例を見る】
融雪洪水と言ってしまうと、雪解けによって大量の雪解け水が川に流れ込み、夏の大雨のように「氾濫」を起こすイメージになってしまいますが、日本国内では、そもそも大規模な河川では夏の大雨に対応した水害対策が既にある程度行われた環境となっています。
すなわち、過去に類を見ないような現象が起きる場合は話は変わりますが、現実的に「融雪」だけによって、一般的に知られているような「大きな河川が氾濫」し、「市街地に大きな被害」をもたらすことは考えにくいと言えます。但し、新潟の信濃川をはじめ、雪国の河川は雪解けシーズンにはかなり増水するため、川に近づいた際の危険度は高くなります。
被害 死者1名・床上浸水28棟・床下浸水61棟・建物一部損壊1棟
近年のまれな事例としては、2018年3月9日に北海道の中小河川で発生した洪水が挙げられます。こちらは、急速に発達する低気圧によってまとまった雨と気温上昇が発生し、結果として一気に雪や氷が解けて発生したものですが、単なる雪解けに伴う融雪洪水というよりは、「凍った川の氷が割れて川をせきとめて」発生した「アイスジャム洪水」と呼ばれるものでした。
但し、アイスジャム洪水のように、物理的に川がせきとめられるような状況になると、川をどのくらいの水が流れるのかは余り関係なくなってしまうため、川が凍るような気温が非常に低い地域(かつ都心部のように川が整備されていない地域)ではリスクはやや高くなると言えるでしょう。
例えば2020年3月9日には、気温上昇と大雨が重なった影響で、北海道内の広い範囲で一時的に雪解け水が集中し、道内の一部では住宅などがある一帯も含めて冠水するなどの被害が生じました。
なお、この際には1日で30cm程度の雪解けが進んだ場所があったため、大きな被害はなかったものの、大規模な河川である釧路川も「氾濫警戒水位」に達するなど、かなりの規模の増水が発生しました。
また、融雪洪水とは言えないものの、特に札幌市内など都市部においては、積雪が多い中で気温が急上昇した際に、「除雪不足」の「生活道路」が半分水たまりと化したザクザクの「ぬかるみ」のような状態になり、結果として自家用車を出すことが困難になるような現象も見られます。
いわゆる「融雪洪水」よりは、恐らくはこういった身近な融雪による影響が、大半の方にとっては大きな影響を及ぼすものと言えるでしょう。
まれに地すべりのリスクも
要因としては、急速な雪解けやまとまった雨によって雪解け水などが地中に流れ込み、「地下水」の水位を上昇させることによって生じるものとなっています。
まとめ
札幌における「雪解け」については、上記の記事で別途解説しております。